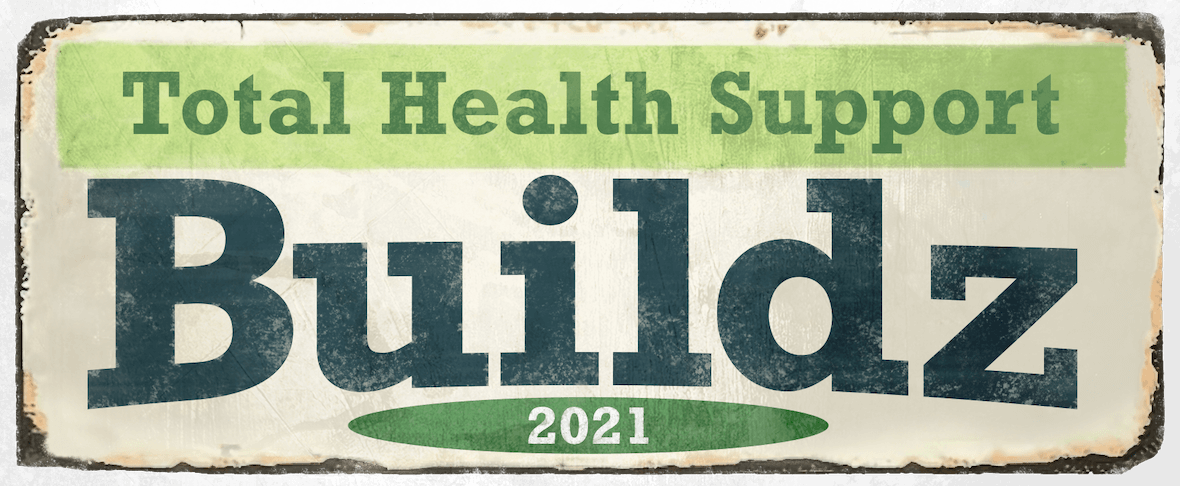
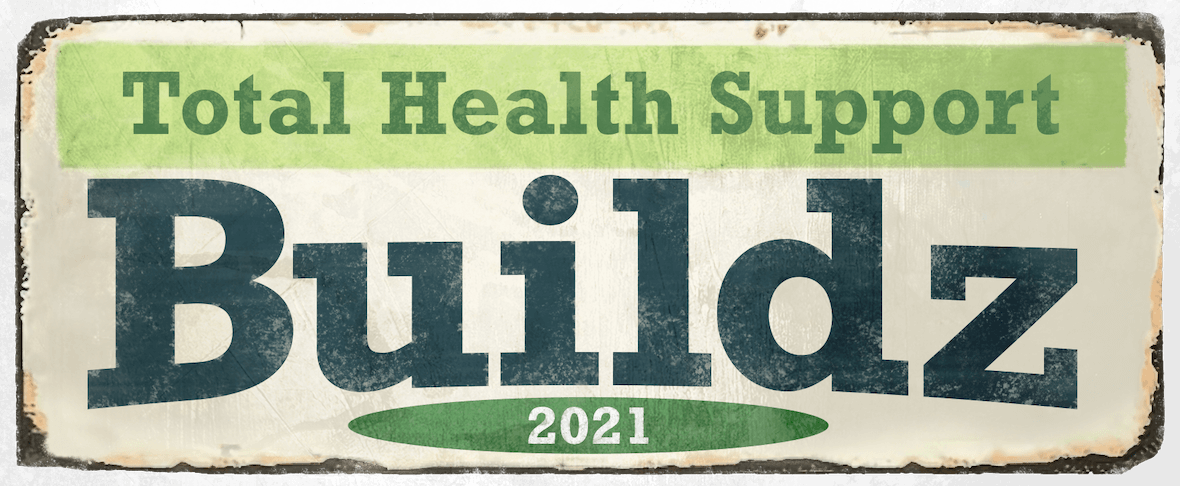

2025.1.14 / ももたろう
介護疲れは、多くの介護者が抱える深刻な問題です。知らず知らずのうちに身体的・精神的負担が積み重なり、「もう疲れた」と感じる方も少なくありません。この記事では、介護疲れの原因と対策を詳しく紹介し、つらい状況を少しでも軽減する方法を提案します。介護疲れを解消することで、心身の健康を保ち、質の高い介護を永く続けられることができるようになります。最後までお読みいただき、少しでも介護疲れを軽減するヒントを見つけてください。

身体的疲労とは、要介護者の身体介助によって生じる、介護者自身の体の疲労や痛みのことを指します。
身体介護(要介護者を起こしたり、支えたりすること)は、介護者の身体に大きな負担がかかります。また、同じ姿勢を長時間保持することで、肩こりや腰痛を引き起こすこともあります。夜間の不眠も介護者の身体的負担となります。
このような身体的負担が蓄積することにより、介護者は慢性的な腰痛や肩こり、睡眠不足に悩まされ、思うように介護できない状態に陥ってしまうのです。
精神的疲労とは、介護することでかかる精神的なストレスや不安感のことです。
介護は、要介護者の状態に常に気を配り、先の見えない状況と向き合い続けなければなりません。認知症の方の介護では、コミュニケーションがうまく取れなかったり、徘徊や暴言などの問題行動に悩まされたりと、精神的な疲弊は大きくなります。また、一人で介護をしている場合には、周囲に理解者が少なく、自分の時間が持てないといった社会的な孤立も、介護者のストレスを高める要因の一つです。
このような精神的負担を抱え続けることで、介護者はうつ状態に陥ったり、感情のコントロールが難しくなったりと、心の健康を損ねるリスクが高まるのです。
経済的疲労とは、介護に必要な費用がかさむことによる経済的な苦労のことを指します。
介護サービスを利用すれば、費用の一部は介護保険から支給されますが、それでも利用者負担分は少なくありません。特に、要介護度が重度の方の介護では、サービス利用料が高額になる傾向にあります。また、仕事と介護の両立が難しくなり、介護離職を選択せざるを得ない状況では、収入が減る一方、支出は増えていきます。
介護費用の負担が重くのしかかることで、介護者は経済面の不安から逃れられず、精神的にも追い詰められていくのです。

介護疲れを起こしやすい人には、以下のような特徴があります。
これらの特徴を持つ方は、介護の大変さに自分を見失い、追い詰められてしまう危険性が高まります。
介護疲れを防ぐためには、「完璧を求めすぎない」「上手に助けを借りる」「自分の時間を作る」ことが大切です。
周囲のサポートを得ながら、柔軟な考え方を心がけることが、介護者自身の心と体を守ることにつながるでしょう。

介護者の中で、介護に関する悩みやストレスを感じている人の割合は年々増加しています。
厚生労働省の調査によると、介護者の約70%が何らかの不安や負担を抱えているという結果が出ています。家族の介護をする上で、身体的・精神的・経済的な負担が大きくのしかかるためです。
また、要介護者の介護度が高くなればなるほど、介護者の疲れも大きくなる傾向にあります。常に目が離せない状態が続いたり、自分の時間が持てなくなったりと、休まる間もなく介護と向き合わなければならないことが、介護者を疲弊させているのです。
参考:厚生労働省「平成28年 国民生活基礎調査の概況」

介護疲れを和らげるためには、自分一人で抱え込まず、さまざまな支援を上手に活用していくことが大切です。
介護保険サービスや介護保険外サービス、行政サービスなどを利用して、介護の負担を分散させましょう。
また、身近な人や専門家に悩みを相談できる環境を整えておくことも重要です。介護の知識やスキルを身につけることで、効率的なケアが可能になり、介護者自身の負担も軽減されます。
介護疲れと上手に付き合っていくには、自分一人で頑張りすぎないことが何より大切なポイントと言えるでしょう。
それぞれについて解説します。
介護保険外サービスとは、介護保険の対象とならない生活支援サービスのことを指します。利用者の個別ニーズに合わせて、柔軟なサービス提供が可能であるのが特徴です。
介護保険外サービスを提供する事業者は、地域の社会福祉協議会やNPO、民間企業など様々です。インターネット検索や、地域包括支援センターなどから情報を集めてみましょう。
ひとり親家庭の介護や障害のある方の介護など、特別なニーズを抱えている場合は、介護保険外サービスを活用することで、より柔軟できめ細やかなサポートを受けられる可能性があります。介護の状況に合わせて、介護保険サービスとうまく組み合わせながら利用していくのが効果的です。
北九州市で家事・生活支援や通院の付き添いは、ももたろうサービスがあります。プロのスタッフによる質の高いサービスを、必要な時に必要な分だけ利用できるのは、介護者の負担軽減につながるでしょう。介護で困ったことがあれば、ぜひももたろうにご相談ください。
介護の仕方がよくわからないことが、介護者のストレスを高める要因の一つとなっています。
介護の知識やスキルを身につけることで、効率的で安全なケアが可能となり、介護者自身の心理的な負担を軽減できるのです。
知識やスキルは、介護者の自信にもつながります。前向きに介護と向き合える心の余裕を生み出す上でも、学びを積み重ねていくことは欠かせないと言えるでしょう。

介護疲れは、身体的、精神的、経済的な負担が原因で引き起こされ、介護する人の多くが経験する深刻な問題です。放置すると、介護者と要介護者の共倒れや虐待などのリスクが高まります。特に認知症の介護は負担が大きいですが、介護保険サービスや行政サービスを活用し、周囲に相談することで、介護疲れを軽減できます。
また、介護の知識やスキルを身につけることで、より効果的なケアが可能となります。介護疲れを感じたら、一人で抱え込まずに周囲のサポートを積極的に受け、介護者自身の心と体を大切にしましょう。