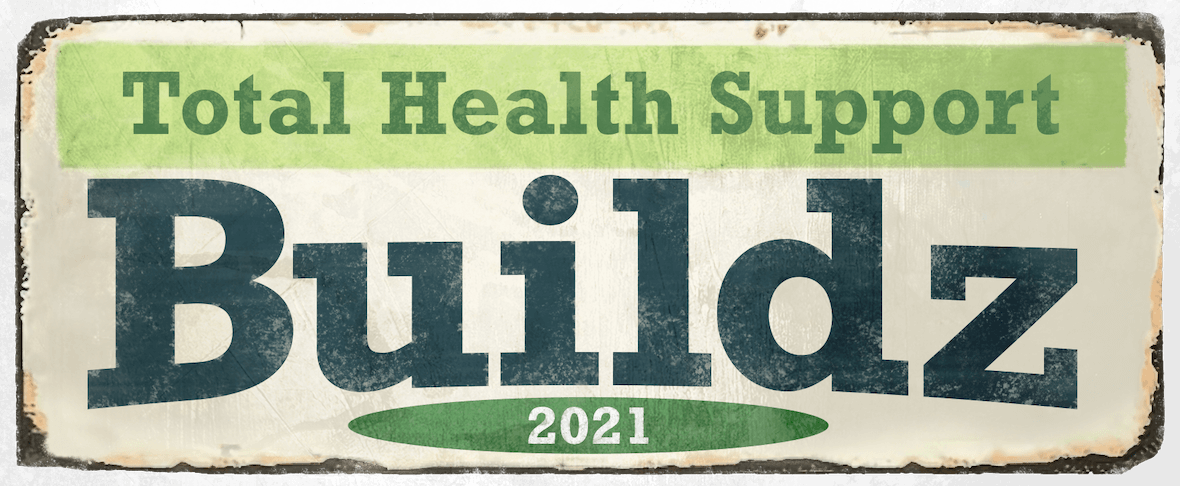
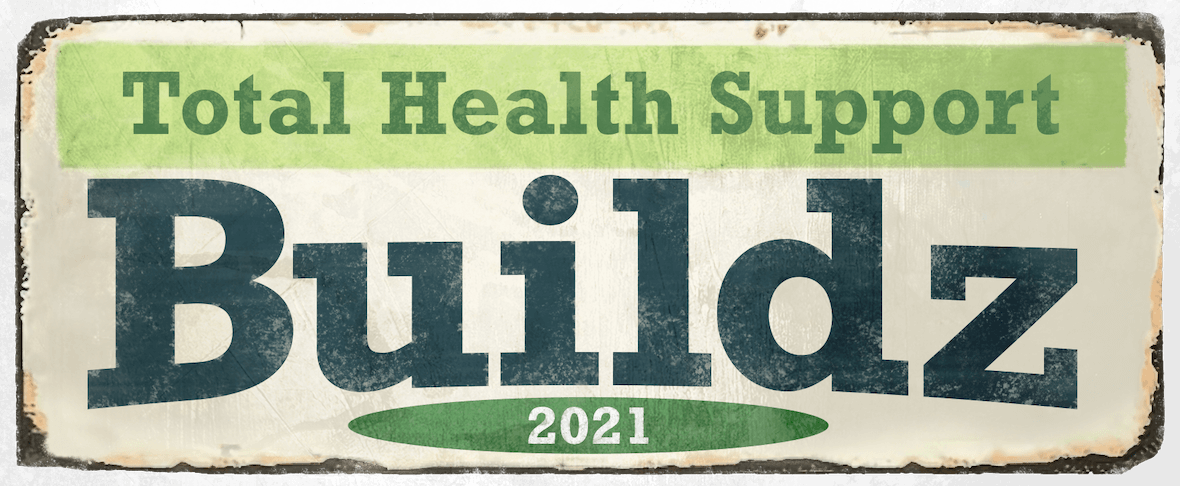

2025.7.1 / ももたろう
子育てや介護をしながら働く皆さんにとって、仕事と家庭のバランスを取るのは大変だと思います。そんな悩みをサポートしてくれるのが「育児・介護休業法」です。この法律、1991年にスタートして以来、時代に合わせて何度もアップデートされてきたました。特に2025年の改正では、働く男性や女性、介護をする人にとってさらに使いやすくなるポイントがたくさんあります。今回はこの法律の基本と、2025年の改正ポイントを一般の方向けにわかりやすく解説します。

正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。短縮されて「育児・介護休業法」と呼ばれます。この法律の目的は、子育てや介護をしながらでも仕事を続けられる環境をつくることとされています。具体的には、以下のような制度を提供することで、働く人をサポートします。
・育児休業:赤ちゃんが生まれたとき、一定期間仕事を休める制度。
・子の看護休暇:子どもの病気や学校行事で休みを取れる制度。
・介護休業:家族の介護が必要なときに休める制度。
・介護休暇:短期間の介護のために休みを取れる制度。
・時短勤務や残業免除:育児や介護中でも働きやすいように、労働時間を調整できる制度。
この法律は、正社員だけでなくパートや契約社員も対象(一部条件あり)。つまり、どんな働き方の人でも、子育てや介護と仕事を両立できるようにサポートしてくれるんです。企業にはこれらの制度を整える義務があり、従業員が制度を使いやすい環境を作ることも求められています。

日本は少子高齢化が進んでおり、働く人が減っているのが現状です。特に、子育てや介護のために仕事を辞めてしまう人が多いと、企業にとっても社会にとっても大きな損失となります。そこで、この法律は「仕事を辞めずに済むように」サポートし、再就職もしやすくすることを目指しています。
男性も女性も、家庭と仕事を両立できる社会をつくることが重要であることが認知されてきました。

2025年4月と10月に、育児・介護休業法が大きく改正されます。今回の改正は、
「もっと柔軟に働けるように」「男性も育児に参加しやすく」「介護で辞めないで済むように」
という3つの柱が中心。以下で、具体的な変更点をわかりやすく解説します。
子育て中の男性や女性がフルタイムで働くのは大変ですよね。特に子どもが3歳を過ぎると、育児休業は終わってもまだまだ手がかかるものです。2025年の改正では、3歳から小学校入学前の子どもを持つ人に、柔軟な働き方をサポートする制度が強化されます。
テレワークの導入が努力義務に
3歳未満の子どもを育てる人向けに、企業はテレワーク(在宅勤務)を導入する努力が求められます。例えば、「保育園のお迎えがあるから早めに帰りたい」というとき、在宅で働ければ時間に余裕ができますよね!
時短勤務の代替としてテレワークを追加
時短勤務が難しい仕事(例えば、工場や接客業)でも、テレワークを代替案として提供できるようになります。
柔軟な働き方の選択肢を義務化(2025年10月施行)
3歳から小学校入学前の子どもを持つ労働者向けに、企業は以下の選択肢から2つ以上を提供し、労働者はその中から1つを選べるようになります。
・時短勤務
・フレックスタイム制(働く時間を自由に調整)
・テレワーク
・始業・終業時刻の変更
・その他、育児に役立つ措置
さらに、企業は労働者にこれらの制度を個別に説明し、希望を聞くことが義務になります。そのため、家庭の環境に応じた働き方が可能になります。
「子の看護等休暇」の対象が拡大
これまで「子の看護休暇」は小学校入学前まででしたが、小学校3年生までに拡大されます。さらに、病気やケガだけでなく、学級閉鎖や入学・卒業式でも休めるようになります。
残業免除の対象も拡大
残業免除を申請できる範囲が、3歳未満から小学校入学前までに広がります。「子どものお迎えがあるから残業は難しい」という場合、気軽に申請できるのは嬉しいポイントです。
育児時短就業給付の新設
時短勤務で収入が減ってしまう人向けに、「育児時短就業給付」という新しい給付金が導入されます。経済的な心配を減らしながら子育てと仕事を両立しやすくなります。
日本では、女性の育児休業取得率は85.1%と高いのに、男性13.97%2021年度)とまだまだ低いのが現状です。 そこで、2025年の改正では、男性が育児休業を取りやすい環境をさらに推進します。
育児休業取得率の公表義務が拡大
これまで従業員1000人超の企業だけが、男性の育児休業取得率を公表する義務がありましたが、2025年4月からは300人超の企業にも拡大となります。
個別の意向確認が必須
妊娠や出産の申し出があったとき、企業は育児休業や柔軟な働き方の制度を個別に説明し、希望を確認する必要があります。これで、「育休取りたいけど言いづらい…」という雰囲気が減り、男性も気軽に育休を申請しやすくなります。
家族の介護が必要になると、仕事を辞めてしまう人も少なくありません。
これを防ぐため、2025年の改正では介護が必要な家庭にも手厚い支援があります。
介護休暇の取得条件が緩和
これまで「入社6ヶ月未満の人は介護休暇を取れない」というルールがありましたが、廃止となりました。入社してすぐでも、家族の介護が必要なら休暇を取れるようになります。
テレワークの努力義務
介護が必要な家族を持つ人にも、テレワークを導入する努力が企業に求められます。
介護制度の周知と意向確認が義務に
介護が必要になったと申し出た従業員に対し、企業は介護休業や支援制度を個別に説明し、希望を確認する義務ができます。さらに、40歳など早い段階で介護に関する情報を提供することも求められます。これで、「いざ介護が必要になったけど何をすればいいかわからない」という状況を防げます。
この法律と共同で動いている「次世代育成支援対策推進法」も、2035年3月31日まで有効期限が延長されました。
企業には、育児休業取得率や労働時間の目標を設定する義務が追加され、働きやすい職場づくりがさらに進むとされています。

育児・介護休業法で、企業には以下のような対応が求められます
・就業規則の見直し:テレワークや時短勤務のルールを明確に
・相談窓口の設置:育児や介護の悩みを相談できる窓口を用意
・従業員への説明:制度の説明や希望の確認をしっかり行う
・公表の準備:300人超の企業は、育児休業取得率を公表する準備
働く人にとっては、柔軟な働き方が選びやすくなり、育児や介護の負担が減るのが大きなメリットとなります。
給付金の新設で収入面の心配も軽減されますし、男性も育休を取りやすくなるので、夫婦で子育てを分担しやすくなります。
また、介護が必要な人も、仕事を辞めずに済むサポートが増えるのは心強くなります。

育児・介護休業法は、子育てや介護をしながら働く人を応援する法律です。
2025年の改正では、特に柔軟な働き方の選択肢が増えること、男性の育児参加が促進されること、介護離職を防ぐためのサポートが強化されることがポイントとなります。企業も従業員も、この改正をきっかけに「働きやすい職場」を一緒につくっていけるようになります。