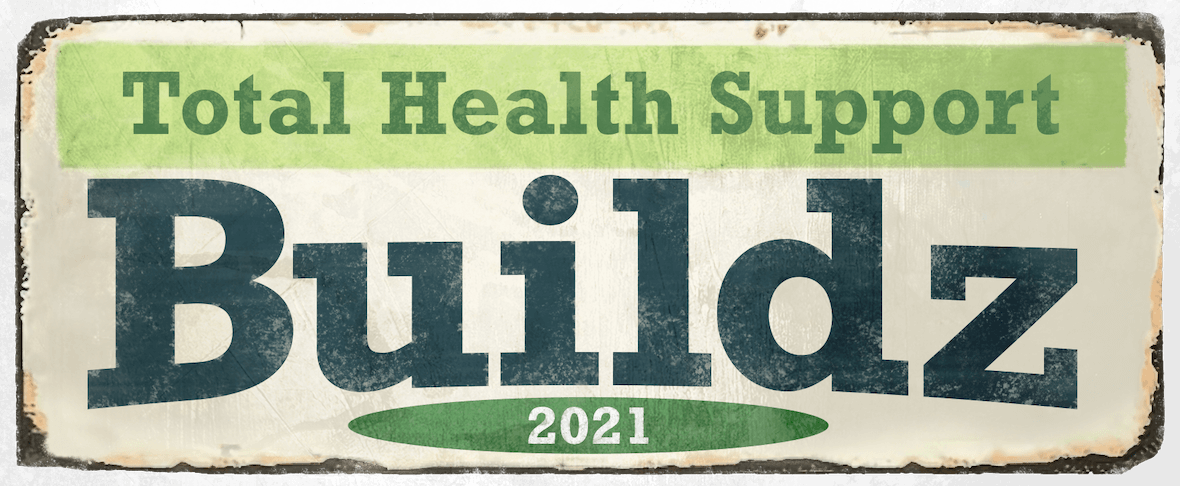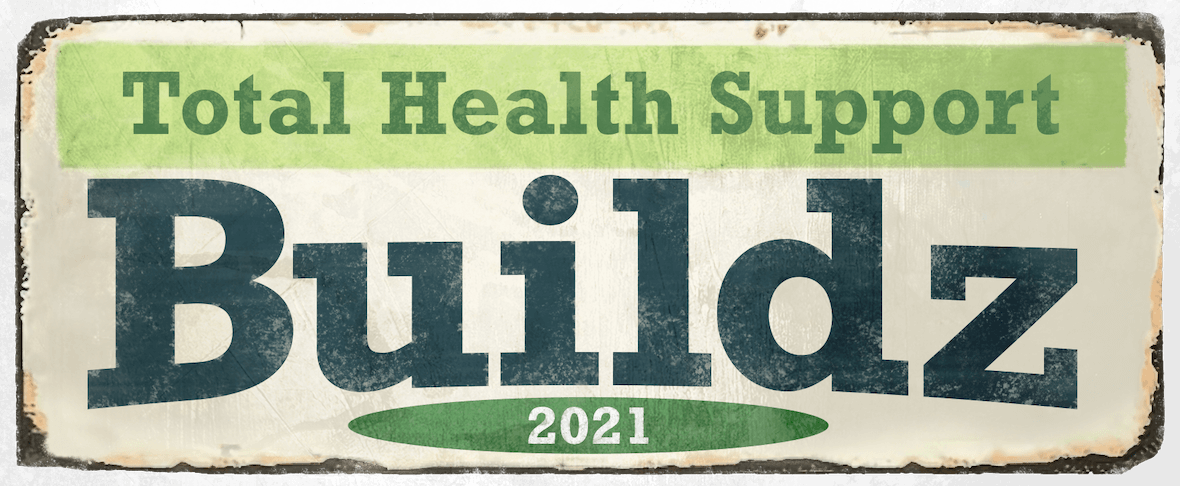こんにちは!
北九州市を中心に保険外看護・リハビリ・介護・見守りサービス「ももたろう」を提供している
株式会社Buildzの佐藤です!
本日は、ももたろうサービスの中でも特にご依頼の多い[通院同行]について注意点と実際の提供内容を含め解説していきます。
①通院同行とは

通院同行とは、病院やクリニックへの通院に不安のある方に、家族や介護スタッフが付き添うことをいいます。例えば、認知症や高齢の方の場合、自分一人では病状についてちゃんと説明できず、また、医療機関からの説明も理解できないことがあるため、家族などまわりの方が病院へ付き添うことがあります。また、足腰が悪い方や疾患を抱えている方が一人で病院まで行けない場合などに、家族やヘルパーさんが帯同し、病院へ付き添います。
②持ち物の確認

病院に行く前に持ち物を確認しましょう。
- 保険証
保険証の他に医療費負担額に関係する証書があれば持参して下さい。この証書も保険証と同じくらい医療費の負担額に関わる重要なものです。例えば70歳から74歳の方なら高齢受給者証、所得区分を記載した証書などがあります。
- 診察券
保険証で代替可能ですが、病院側がカルテなどの情報を早く探すことができます。
- お薬手帳
病院で処方するお薬を選んでもらう時、今飲んでいるお薬の情報があれば、スムーズに処方してもらえます。また、処方箋薬局でお薬を出してもらう時に値段が安くなることもあります。
- 紹介状
他院からの紹介や転院の場合には必ず必要になります。
- オムツ
日常的におむつを使用している方は、待ち時間が長くなることも想定して準備しておきましょう。
- メモ帳
医師からの指示を忘れてしまうこともあるので準備しておくと良いでしょう。
また、介護スタッフも持参しているとご家族への伝達がスムーズで漏れもなく済みます。
③前準備

高齢のご家族がいる方は特にですが、普段から「何かあるかも」と考え、いつでも迅速に行動出来るよう心構えをしておくことが重要です。
いざという時の不安を少しでも軽減して、冷静に行動出来るよう事前に知識などを頭に入れておきましょう。
- 事前に症状や体調の把握
離れて暮らしている、他の家族が介護をしている、認知症を患っているなどの場合は、いざ病院付き添いをしようとしても医師に症状を伝えられないといったことが起こります。
事前に本人や症状・体調をよく知る家族などとコミュニケーションをとっておき、状況を把握しておきましょう。
また、介護スタッフの医師への伝達事項をお伝えしておき指示を仰ぐことも大切です。
- 医師への確認事項(例)
・症状や検査結果
・治療後はどのような状態まで回復が見込まれるか
・どのような治療をするか
・その治療をするとどのような効果があるか、しないとどうなるか
・治療によって起こり得る合併症や副作用、起きた時の対応
・他の治療法はないのか(提案されている治療法との比較) 等
④同行が終わったら

診察の付き添いが終わっても、そこで終わりではありません。
その後の生活を、付き添った側も付き添われた側も安心して送れるように、病院で聞いてきたことの共有や薬の管理など、その時々に合った対応をしましょう。
- 診察内容の共有
ケアマネージャーや家族などの関係者に情報を共有しましょう。施設に入居中の方であれば施設スタッフへの報告も忘れない様にしましょう。自分一人だけで抱えないためにチーム内で共有することが大事です。
メモを取っていればより整理して伝えることが可能です。
- 薬の管理
一包化して間違いなく飲めるようにしましょう。
家族がセットするか、処方箋薬局で一包化してもらいましょう。
処方箋薬局での一包化のデメリットとしては、費用がかかること、途中で薬の内容が変わった時、服用中止になった薬を抜き出すのが難しいなどが挙げられます。
- 「服薬ボックス」「おくすりカレンダー」などを使う
曜日や日付が分かる段階の方であれば、該当時刻の薬服用の有無が確認できるので、有用です。
1日1回のみの服用であれば、大きなカレンダー(暦)に薬を貼っておくだけで上手くいく可能性もあります。
この場合も一包化しておくと、扱いやすく間違えにくいです。
⑤車椅子を利用する場合の注意点

通院に同行する場合に車椅子を使用することは少なくありません。車椅子で病院まで移動する場合は、ベッドから車椅子、車椅子から車などへの移乗介助が必要です。はじめての移乗介助の注意点を6つご紹介します。しっかりと介助方法を理解して細心の注意を払いましょう。
- できる限りベッドと車椅子の位置を近づける
- 車椅子のハンドブレーキをしっかりと固定し、少しの弾みでも車椅子が動かないようにする
- 介助者の腕は相手の腰(背中)に、被介助者の腕は介助者の肩に手を回す
- 介助者は、相手の上半身を自分がいる方向(前方)へ引き寄せるようにする
- 介助者は両脚を広げ、安定した体勢を整える
- 声かけでお互いの意思疎通を図る
身体を無理に動かそうとすると、介助される側に大きな負担がかかるばかりか、介助する側にも余計な負担がかかることになります。身体の動きに合わせ、安心して移乗できるように心がけましょう。
介護保険の通院介助では対応できないニーズに応えるため、自費で利用できる病院付き添いサービスがあります。このようなサービスでは、以下のようなケースにも対応できる可能性があります。
- 診察室で一緒に医師の話を聞く
- 通院のついでにスーパーへ寄りたい
- 複数の診療科を受診する際の付き添い
- 入退院や転院時の手続きや付き添い
このように、介護保険の枠にとらわれず、自由度の高い病院の付き添いをお願いしたい場合は、保険外サービスを利用することをおすすめします。
例えば、「ももたろう」の訪問介護サービスでは、介護保険でカバーしきれない病院付き添いや、単身で暮らす高齢者の見守り、介護相談などを行っています「ももたろう」は福岡県北九州市、中間市、遠賀郡、鞍手郡、宗像市、福津市、直方市など幅広いエリアで対応が可能です。
家族に代わって親御さんや親戚の介護をできる人を探している方や、遠距離のため思うような介護ができないとお悩みの方は、一度「ももたろう」に相談してみることをおすすめします。
⑥まとめ

通院介助は、自宅から病院までの移動や受診手続きなどを支援するサービスで、要介護1~5の認定を受けた方が利用できます。介護保険の適用範囲外の付き添いが必要な場合は、自費の病院付き添いサービスを検討することをおすすめします。高齢者の通院をサポートするさまざまなサービスを理解し、状況に合わせて適切に利用することで、安心して医療を受けることができるでしょう。